→続きます

私は木ノ下歌舞伎の『三人吉三廓初買』は、2014年版、2015年版は見ていないので、単純な比較はできない。今回は東京に引き続き2度目だったのだけれど、すごくよかった。
というか、東京で観たときよりずっとよかった。
(1)それは多分、東京で観たときはいつも見ている歌舞伎にとらわれすぎていたのだと思う。そして、「慣れた」(笑)。
(2)また役者が上演を重ねてさらにバージョンアップした部分もあったと思う。
(3)東京で観たときには「?」だったところが解決した部分もあった。
(4)まだ謎の部分もある。
というわけで、4つに分けて書いていこうと思う。
東京、松本でのアフタートークをどちらも聞いているのでそれも入れ込みながら書いていきたい。てか、もう書いている
(1)東京で観たときはいつも見ている歌舞伎にとらわれすぎていたのだと思う。そして、「慣れた」(笑)。
・上演時間
1幕目 約115分
大川端があって、名乗りを上げて3人が去っていく。さ~休憩かと思うとさらに続いてこれが結構長く感じたのだが、2回目のときはそれがわかっていたせいか楽々クリア。あまり長く感じなかった。
そして、1幕に比べると2幕は短いのであっという間(75分)、3幕に至ってはもう怒涛の如く幕切れまでつっぱしるので、結局5時間越えがあっという間なのだった。
・大川端
さ~!お嬢が「月も朧に白魚の~」という名セリフが出る!ってところで、出ない!ここはお嬢が「金はとった、厄は落とした。ハッピーだぜ!」っていうところだから、現代語で歌にするのは一向にかまわないのだが、やはりセリフまで覚えている名場面だから、聞きたかった。
まあ、松本では、このセリフがないとわかっていたので特に気にならなかった。坂口お嬢のハッピーを味わう。
が、東京では、「えー。ないのー?」と思って引きずってしまって、その後の芝居が入ってこなかった(ということが松本でわかった。置いてけぼりになってしまい記憶がない)
・衣裳
東京で観たときは慣れなかった。なんだかヘンテコな格好だなあって。でも若い人たちはカッコイイ!と叫んでいたから、やっぱり頭が古くて歌舞伎にとらわれすぎているのだろう。そういえば木ノ下歌舞伎はいつもそうだったわね。そして再演時には、時代に合わせて、衣裳を替えているから古臭い感じにならないのであった、そういえば。
でも東京で観たときは(私の頭は古いので)
なんで着物の下にレースのブラウス着ているんだろう。
なんでジャケットなんだろう。
なんでお嬢は黒のテカテカしたのを着ているんだろう。
芸者たちのあの妙な布団みたいな恰好はどうだ?
伝吉は割と違和感なし(笑)。という感じだった。
3幕の丁子屋別荘の場ではさっきまでふとんみたいなのをしょっていた吉野さんたちが現代風のスーツみたいな恰好をしているよ?って感じだった。
しかし、考えてみると江戸時代と明治時代のはざまで、世の中は急速に変化していった。まあ1年でそれほど変わるとも思わないけれど、ファッションに敏感な人は年寄りが突拍子もなく感じる格好はいろいろとしていたことだろう。靴とかドレスなんて舶来ものが入ってきたりしてね。
今だって、年よりが眉を顰めたくなるような着物の着方をしている若い子はたくさんいるもんね。着物の襟もとからレースが覗いていたり、ブーツはいていたり。
そう思ったら、それほど気にならなくなった。花魁たちの布団のような衣裳は最後までちょっと慣れなかった(;^_^A。
そして松本では、三人の吉三の衣裳はものすごく格好よく見えた不思議。
3人は、格好はバラバラなんだけれど黒の衣裳に赤の差し色で統一しており、それがまたよかった。お嬢はなんと着物ではなくビッグパンツ(言い方はこれでいいのか?)だったのね。
木ノ下さんのアフタートークによれば(東京)3人の衣裳は磁石のようにひかれあう3人の統一感をあらわしたとのこと。死のにおいも感じる?
(2)役者について
・三人の吉三郎
実は、東京で観たときに感じたのは、「バランスの悪さ」だった。うまく説明できなくてもどかしいのだけれど、三人の吉三はどの役者も個性的で演技もよかったのに、なんだかバランスが悪い。
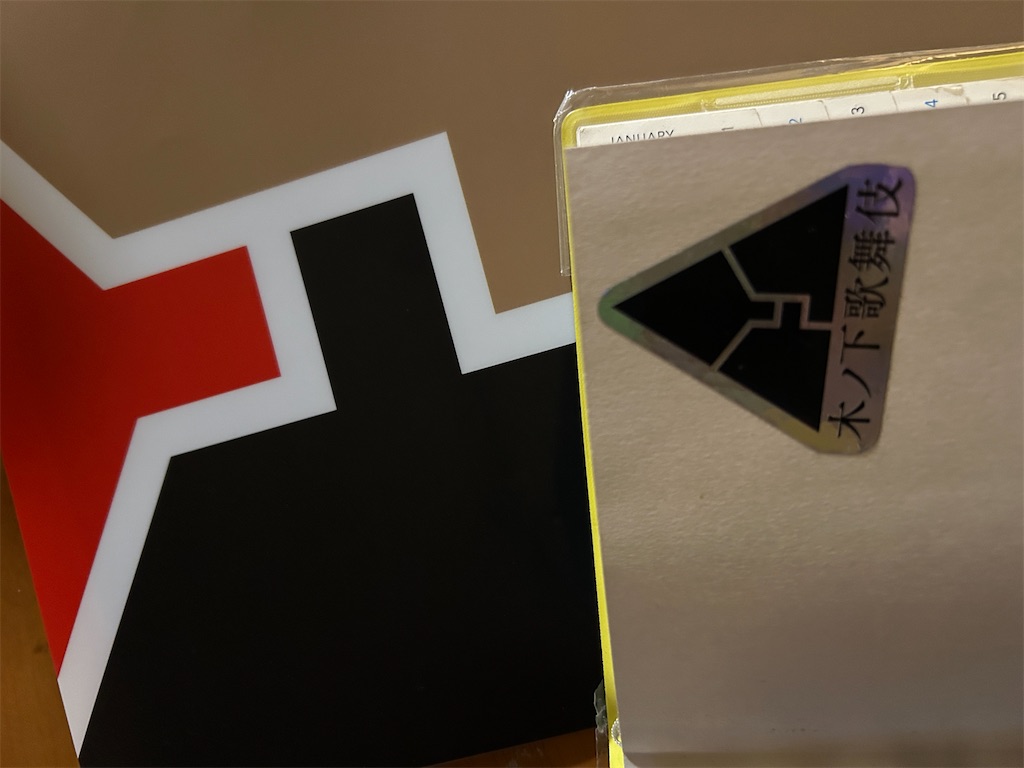
▲これは木ノ下歌舞伎の三人吉三のトレードマーク
このように3人できっちりと三角形が出来ているはずなのにできていない感じがあった(個人の感想ですよ!)。
突出して個性的な坂口涼太郎のお嬢が、ちょっと三角形から飛び出していたのかもしれない。
ところが、松本では全くその違和感を感じなかった。
3人の呼吸が合って来たのか、空気がなじんできたのか。単に私が慣れたのか。
東京ではお坊の須賀健太が坂口涼太郎とちょっと乖離している感じがあったけれど、うまい具合に融合してきて、さらに和尚の田中俊介の存在感がグンっと大きくなって三角形をがっちり固めている感があった。
田中和尚の、真実を知った時の絶望感がこちらの心をぐっさりとえぐった。
須賀お坊は、かわいくてもともと武家の出だからちょっといいとこ坊ちゃんが、ちょい背伸びしている感じがよかった。
坂口お嬢は、感性豊かで面白い役者さんだなあ。ずっと見ていたい。
今私、煮物を作りながらこのブログを書いているんだけれど、酒と砂糖を入れてクツクツ煮て、具が柔らかくなったら醤油を入れる。入れてすぐは「醤油と酒の味だ。醤油がとんがっている」って感じなのに、クツクツ煮ていると味が混然として美味しくなる。そんな感じかなあ。「しょうゆと酒と味醂」だったのが、得も言われぬ美味しい煮物になりました的な。
他の印象的な役者さん
・武居卓
なんと、7役。早替わりもあって「ほんと、忙しい!」とぼやくセリフもウケていた。役の年齢も鉄之助という子どもから金貸し、浪人、源次坊、鬼などまあ幅広く。見ごたえあって出てくるのが楽しみで観客からも新たな役で出てくると拍手がわいていた。鉄之助ちゃんはもちろんだけれど金貸し太郎右衛門が、ずるくてあなどれない感じでよかった。鉄之助ちゃん、3幕では少し大きくなって「芸細かいな」と思いました。
・高山のえみ
『勧進帳』の義経役を見てからもう目が離せない役者さん。今回は花魁吉野。姐さん的な立場の優しい気持ちの花魁で立ち姿とヘアスタイルの美しさにほれぼれ。夜鷹おいぼになるとまたぐらをボリボリ掻く快演。
・川平慈英
土左衛門伝吉とお地蔵さん。お地蔵さんも片言英語っぽくてよかった(笑)。伝吉は、情の深さが際立った。
・緒川たまき
文里女房おしづ。声も姿も美しい。特によかったのは3幕で、丁子屋に向かうところ。傘をかぶって鉄之助の手を引き、相の山がよかったなあ。
相の山というのは、
三重県伊勢の間の山に、簓(ささら)をすったり三味線を弾いたりして唄を歌い、子どもを踊らせ参宮客に物乞いする乞食芸人がいた。その歌や曲節が年に伝わり間の山伏として流行。歌詞は哀切。「新潮日本古典集成 三人吉三廓初買」
とある。要するに、おしづは一重に逢うため、梅吉(文里と一重の子)の身を案じ、身を相の山にやつし、子どもを連れて出かけてきたのだ。普通のいでたちでは、文里の妻ということで話もしにくかろうと、相の山に身をやつしてきた。その時の歌がとても切ないのだけれど、木ノ下歌舞伎ではその歌詞を活かしつつの ラップ !
雪の中、編み笠をかぶって安下駄をはき、胡弓をもち、子どもの手をとってみしみしと歩いてくるおしづがとても絵画的で美しかった。
・おとせ・十三郎
よかった。純真無垢な二人が出会い、結ばれ、実は畜生道に落ちるとも知らずに、兄のためになるならと極楽を夢見て死んでいく。生きているときには辛かった二人なのね。幸せそうな二人であればあるほど、見ていてツライ場面だ。黙阿弥さん残酷や。
2人の心が通い合うシーンはじっくり見せてくれてよかった。どろどろもあって不穏。運命に引き寄せられてしまう二人。ワンワンワンワオーン。
伝吉やおとせ・十三郎が出てくるときには、ちょくちょく犬の遠吠えが聞こえてきて不穏。
→続きます